同志のみなさんへ
今年もあと一週間となりました。みなさん、年の瀬をいかがお過ごしですか。今年も色々ありましたが、私にとっては(おそらく同志のみなさんにとっても)一番の大きな出来事は政治グループ「蒼生」の解散(8月)ではないでしょうか。
勤続40年。もうすぐ「円満退社」かなぁ、と思っていた時の「解散」でした。「誓約者集団」から「解放」された後は、脱原発運動と「緑の党」への(細々とした)関わりを除いて、あとは静かに余生を送っているところです。
さて、今年を振り返って、今年読んだ数少ない本の中から、最も影響を受け、多くの人に読んでもらいたいた本を2冊紹介させてもらいます。
(1)『日本人は何を考えてきたか』(NHK出版)
(2)『フクシマ以後―エネルギー・通貨・主権』(関曠野、青土社)
(1)の書は、「デモとデモクラシー」というテーマを深め、さらに日本民衆運動の中に「緑」の思想を発見していく作業に欠かせない視点を提供してくれています。
この本はNHKの同名のテレビ番組を本にしたものですが、私はこの番組をたまたま見ていました。俳優の菅原文太さんが、福島県浪江町で大和田秀文さん(長いあいだ脱原発運動を担ってこられ)という人を訊ねるシーンがあるのですが、その大和田さんの先祖が、実は福島の自由民権運動のリーダー苅宿仲衛だというのを知った時は、衝撃でした。
私は、数年前から、日本の近代を総括する時、明治維新で誕生した薩長政府が採った路線とは違う、もう一つ別の「日本の近代化」が可能だった、と考てきました。その可能性を会津藩(幕府内「一会桑政権」)、戊辰戦争の「賊軍」奥羽越列藩同盟、そして、東北の地からの「自由民権運動」という系譜で探っていたのですが、福島原発事故という新しい状況の中で、NHKがすばやく、私とほぼ同じ視点で、日本の近代化を相対化するすぐれた番組を作りあげてしまったことに驚嘆しました。
★参考
NHK・Eテレ「日本人は何をかんがえてきたか」
2013年1月から「昭和編」が始まるのを機会に、正月早々「明治編」「大正編」 の再放送があります。
http://www.nhk.or.jp/nihonjin/index.html
そして、この番組(本)に触発されて、私は、この番組の中でも紹介されている30年前のNHK大河ドラマ「獅子の時代」のDVD、14巻・53話を全部みてしまいました(8月、9月、10月)。
さらに、偶然が続くのですが、私がこの「獅子の時代」を見ている時に本屋でたまたま『新しい左翼入門』(松尾匡、講談社新書)という本を立ち読みしていたら、なんとこの本のネタになっているのが「獅子の時代」ではありませんか。
どういうことかと言うと、明治以降の日本の民衆運動の歴史を、政府の側に参加して善政を実現しようという道(「獅子の時代」の薩摩藩士・苅谷嘉顕<加藤剛>の立場)と、悪政に現場から抵抗し続ける道(会津藩士・平沼銑次<菅原文太>の立場)の相剋として描き、その対立をどう超えていくのか、というテーマ設定です。
脱原発のデモと議会制の関係が話題になっていたこの夏に出版され、しかも福島に関係することもあり、結構売れているようです。(念のために言っておくとこの本には「新左翼」の総括は出てきません)
ここでちょっと脇道にそれますが、松尾匡さんについてひとこと。
松尾さんは「左」の人で「理論経済学」が専門のようですが、日本の既成左翼、新左翼とは異なり、かなり柔軟な人のようです。今話題の「アベノミクス」に対しても、本来、左翼が主張すべき内容である、という立場です。なるほどクルーグマンや、ステグリッツも日本のデフレ対策として「財政出動」と「金融緩和」を主張していましたね。
さらに、アメリカのリベラルだけではなく、欧州社会党や欧州左翼(共産党、新左翼くむむ)も「質の高い完全雇用の実現」をかかげ、そのために「欧州中央銀行を民主的にコントロール」して「金融緩和を実現させよ」という立場のようです。(松尾匡『不況は人災です!』筑摩書房を参照)
「中央銀行の独立性」などという幻想は、欧州の左翼、民衆運動には無縁だということがよく分かりました。そう言えば、ユーチューブで見たアメリカのオキュパイ参加者が「FRBを解体せよ!」と叫んでいましたが、日本の民衆運動は、まだ「日銀を解体せよ」には至っていませんね。
★参考
松尾匡のページ
12年11月24日 欧州左翼はこんなに「金融右翼」だぞ~(笑)
http://matsuo-tadasu.ptu.jp/essay__121124.html
話を本筋に戻します。来年のNHKの大河は「八重の桜」です。明治維新を敗者(会津)の側から描くのは「獅子の時代」以来じゃないでしょうか。本屋には、新島八重モノであふれています。総選挙で「維新の会」が大幅に議席を増加させた要因の一つに、日本人の中に「明治維新」(薩長政府に対する)をプラス価値として評価する歴史観が色濃くあることが指摘できます。「八重の桜」がヒットして、このあやまった歴史観が相対化されよう期待しています。
(2)『フクシマ以後―エネルギー・通貨・主権』(関曠野、青土社)
この本は、先ほど取りあげた「アベノミクス」を擁護するのではなく、これを根底的に粉砕する理論的視点が得られる貴重な本です。低成長の時代のマクロ経済のあり方を、英国のC・H・ダクラス(1879~1952)の「社会信用論」を援用しながら「政府通貨」(地域通貨)「国民配当」(ベーシンクインカム)「公正価格」(中小零細、自営業者への所得保障)の3大話としてまとめています。
「脱成長」の社会を展望するなら「中央銀行」や「銀行券」や「租税国家」という経済成長の時代に固有のシステムを脱ぎ捨てなければならない、というわけです。こうした視点からは、800兆円と言われる日本国の借金(国債)など踏み倒してしまっても誰も困らないことになります。
このダクラスの理論、学的世界でどう評価されているか分かりませんが、私は、もっと左翼・脱成長派が取り入れるべきと思います。私も最初は「トンデモ論?」と思いましたが、今は、マルクスの理論が恐慌の中に革命を見る経済学であるのに対して、ケインズの理論は、恐慌の中に新しい成長へのトバ口をみる経済学、この両者に対してダグラスの理論は、成長が終わった段階で(あるいは、終わらせるために)環境と経済の循環を可能にする経済学、というふうに理解しています。
安倍と自民党が先祖帰りして、新自由主義者にとっては本来は敵であるはずの「新しいケインズ主義」の政策を大胆に実施しようという時代です。敵も必死なのです。しかし策がないのです。
成長の終わった世界の変化に逆らって、無理に無理を重ねて成長を追い求めて、結果的にハードランデングして社会を壊してしまうことを、私は最も恐れます。その前に、脱成長の社会に合わせて、社会全体をソフトランデングさせていくシステムの構築が必要です。ダグラスの「社会信用論」はその指針と成りうると思うのですが、いかがでしょうか。
★参考
C・Hダグラスの「社会信用倫」や関曠野さんの講演録を下記の
「ベーシックインカム・実演を探る会」のサイトで読めます。
http://bijp.net/
上記の本と同様に、金融危機・恐慌の中に新しい社会の始まりを見る、という立場から書かれた関連本をいくつか紹介しておきます。まだ読了前のもありますが(^^;)
●『通貨進化論―「成長なき時代」の通貨システム』(岩村充、新潮選書)
「銀行券に変わるものを作れ」と主張。
著者は元日銀マンだから説得力有りすぎ。
●『「通貨」はこれからどうなるか』(浜矩子、PHP新書)
基軸通貨は無くなって通貨の多様化、地域通貨の時代がくる。
●『資本主義の「終わりの始まり」―ギリシャ、イタリアで起きていること』
(藤原章生、新潮選書)
効率性に無頓着なギリシャ社会に「資本主義」を越える扉をみる。
あとがきで岩村充の『通貨進化論』を高く評価。
●『アイスランドからの警告―国家破綻の現実』(アウスゲイル・ジョウンソン、新泉社)
アイスランド市民は大手バンクの救済も、国家債務返済も拒否して破綻を選択。
しかし、銀行システムを失った代わりに「幸せ」を手に入れた。
●『<借金人間>製造工場―負債の政治経済学』(マウリツィオ・ラッツート、作品社)
金融資本主義の本質は、負債によって国家と民衆を支配・管理するシステムである
以上、長々と書いてしまいました。来年のことについても(参院選や緑のこと)少しはふれておかねければなりませんが、それは、またの機会にしましょう。
こらから猛烈な寒波が日本を襲うとか。ホワイトクリスマスになるのかな。
また、ノロウイルスが猛威をふるっているようですが、みなさん、お体をお大事に。
それじゃ、また。
投稿時間 : 10:14 個別ページ表示 | トラックバック (0)
リーフレットの一部を抜粋します。
『ハーフ オプション 軍事費を半分に!―市民からの提言』
青木雅彦著
A5判 総334頁
一冊 1995円(税込)、送料340円
草莽社(京都市)刊
ISBN978-4-915480-12-6 c-0031
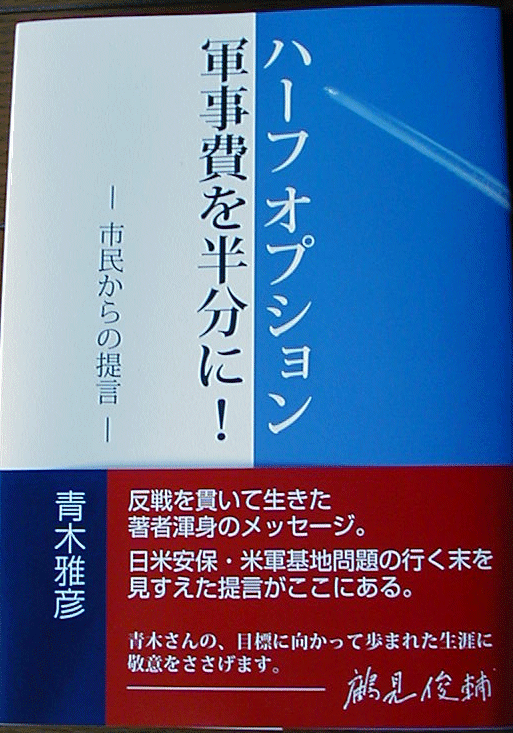
彼は死ぬまで戦争に反対するという意思を表明して生きた。
私は彼を目標にしたいと思うし、そのように生きて終わりにしたいと思う。
―鶴見俊輔氏「序」より
2008年の春、
志半ばで亡くなった、一人の反軍・反戦活動家がいた。
名前は、
青木雅彦という。
大きな声でさけぶわけでなく、華々しく成果をうたうこともなかったが、
その、鋭利な知性は、地道に、確かに、日本の平和運動に足跡を残した。
一九九一年、軍事費半減への具体的道筋を示す提言として唱えた「ハーフ オプション」論は、大きな反響をよぶところとなる。
その後も知性とアイデアを駆使して、様々な活動を展開し、
その著述と膨大な発信を続けた。
その揺るぎない平和への信念は、
おどろくべきエネルギーの蓄積として残された。
今、あらためて新鮮な、青木雅彦の軍縮への提言を、
混迷の時代に問う。
日本の軍事費を半減させよう。
いや世界の軍事費を半分に減らそう。
それを原資に、災害救助、難民対策、飢餓や貧困対策、
環境保護などの基金として生かす制度を作ろうと呼びかける。
これは核兵器廃絶よりも、困難を伴うだろう。
しかし世界の軍事費を半減させようというスローガンは、
今という時代にこそ、多くの市民の共感を得られるはずである。
(湯浅一郎氏「解説」より)
【青木雅彦 あおき まさひこ】
1955年、兵庫県篠山町(現篠山市)に生まれる。関西学院大学、さらに京都大学に進み、反体制情報センターなどを皮切りに、反軍・反戦組織を次々と立ち上げ、多くの文章を発表する。
その博識と語学力をもとに、実証的、創造的に読み解いた状況分析と平和への「実現主義」は、幅広く運動に影響を与え、貢献した。
2008年 逝去。
<お申込み>
郵便振替口座 009940-3-272182 青木雅彦著作 出版委員会
1冊2,335円(税込・送込) 2冊4,440円 *書店でもお求めいただけます。
■出版賛同金もお願いしています。
1口 5,000円(3冊謹呈いたします)
青木雅彦著作 出版委員会 代表 足立修行
電話/ファックス 0774-330851
投稿時間 : 17:03 個別ページ表示 | トラックバック (0)

本書のタイトルとなっている「生活保障」という言葉は平易ではあるがなじみのあるものではない。著者はこれを「雇用と社会保障を結び付ける言葉」として使う。その生活保障が大きく揺さぶられるようになって久しい。様々な処方箋が語られるが、本書の特徴は、新たな生活保障の再生ビジョンを「アクティベーション型生活保障」として提唱するところにある。
では「アクティベーション」とは何か。それは社会保障を就労促進につなげる社会政策のことである。一般にそれらの政策は「ワークフェア」と呼ばれるが、福祉受給者を就労に駆り立てる面が強いアメリカのそれと区別して、デンマークやスウェーデンの就労支援サービスを「アクティベーション」と呼んでいる。つまり「自助のための公助」である。
本書が紹介する「スウェーデン型生活保障」から学ぶべき点は多い。社会保障・サービスで雇用を支えて人々の多用な選択を保障している。
例えば「働きながら学ぶ」ことへの支援。よく知られるのが高い生産性部門に異動するためのスキルアップのための職業訓練サービスであるが、それだけに留まらない。「コンブクス」と呼ばれる自治体が提供する生涯教育サービスがある。働く若年層であれば多くて週に7500円ほどの「学習手当」が給付される。25歳以上だと更に週に5000円ほどが「追加貸与」される。また働く大人には「教育休暇制度」があり、学ぶための休職が保障されている。「雇用保障と社会保障の連携によって、人々が働く場に参入し、あるいは離脱するチャンスを拡大した」のである。
さらに、社会保障が家族との結びつき、広くは著者が重視する「生きる場」を充実させることに役立っている。480日の育児休暇制度(内390日は従前の所得の八割保障)。結果として一歳未満乳児の公認保育サービスの利用率はゼロ%だという(日本7%)。
あるいは「近親者介護手当」(看取り休暇)。家族か否かを問わず「人生でかけがえのない人が重篤の時」最長60日間の休暇が取得できる(その内45日間は従前の所得の約八割が保障される)。
日本ではかけ声だけの「ワークライフバランス」がスウェーデンでは確かに実践されている。
本書は、こうしたスウェーデンの生活保障の紹介の上に、後半部分で、日本における雇用と社会保障の「連携の新しいかたち」「排除しない社会(交差点型社会)」のビジョンを提起している。労働市場の規制を伴う生涯教育、労働の見返りを高める最低賃金アップ、安定した仕事のワークシュアリングなどの政策群は新自由主義とは明らかに違う。また「第六次産業」の育成などによる雇用の創出を目指す方向は「第三の道」を超えている。とりわけ著者が「交差点型社会」と呼ぶ労働市場と外部を自由に往来可能とする制度は、多用なライフサイクルの可能性を感じさせる。
* * *
だが、こうした「アクティベーション型生活保障」は著者が言うように「人々をひたすら労働に駆り立てるものではない」かも知れないが「労働市場への参加」を良しとする点でワークフェアと同じではないか。
生活保障ということであれば無条件(=労働を条件とせず)に生活に必要な現金を給付するベーシックインカムの考え方がある。しかし著者は本書で事実上その構想を斥けている。理由として政治的合意の難しさ、持続性への疑問を上げている。持続性への疑問とは「ベーシックインカムには就労を軸とした社会参加を拡大していく具体的な仕掛けがな」く、「人々が隠遁生活を強めることもありうる」からだという。隠遁生活が経済成長を停滞させるというわけだ。
こうした、ベーシックインカムに対する著者の否定的な評価には正直戸惑う。なぜなら、著者はかつて「脱生産主義の福祉ガバナンス」として「ベーシックインカムの可能性」を高く評価していたからである。逆にアクティベーションとワークフェアについては次のように論じていた。
「ワークフェアとアクティベーションもまた、人々を労働市場に動員しようという点でともに生産主義の発想を引きずっていた。ところが、この生産主義そのものが限界に突き当たっている可能性が強くなっている」(『思想』06年3月号)。
新しい福祉ガバナンスが挑戦すべき課題は、リスク構造の変化への対応に加えて、環境制約による定常型社会(脱成長社会)への対応であろう。本書ではこの視点がすっぽりと抜け落ちているのは残念だ。
もう一つ、本書への疑問は、アクティベーションで本当に「排除しない社会」を作れるか、という問題だ。本書ではスウェーデンの福祉国家を支えている規範として「アルベーツリーエン」という言葉を紹介している。「就労原則」と著者は訳しているが、要するに、みんなで働いて福祉国家を支えよう、という含意だという。こうした社会規範が長年に渡ってつくられ、制度もそれに応えるために給付は所得に比例させている。スウェーデンにおける福祉とは「最低保障」ということではなく「現在の生活水準の維持」を手助けしてくれるもの、との了解だという。
しかし、これは、見方(立場)を変えると、かなりツライ社会ではないか。働いていない人はどうなるのか。「高福祉高負担」の「社会契約」の社会ではフリーライダー(ただ乗り)は許されない。著者も別のところで「日本人が思っている以上に不就労に対しては厳しい社会でもある」と語っている。
また、著者の交差点社会の構想は、労働市場と外部社会との自由な往来を保障する社会であるが、交差点の中心に存在しているのはやはり労働市場であった。さらに、その労働市場の内部では、低熟練労働から高い生産性を担いうる高度な労働への移行が「一方通行的」に奨励される。
この点について日本では「雇用」が「社会保障」を代替してきた関係で、すでに充分に「不就労に対しては厳しい社会」である。またスキルアップ(志向)が査定に大きな比重をしめるので、そのことが働く者のメンタル破壊を生んでいる。この息苦しい労働中心社会に風穴をあける作業が焦眉の課題だ。
「労働市場」を社会の中で小さな比重にし、「生活保障」を「労働」と分離する方向こそ、社会と人々を活性化させる道だと思う。
『生活保障―排除しない社会へ』宮本太郎/岩波新書/800円
投稿時間 : 00:00 個別ページ表示 | トラックバック (0)
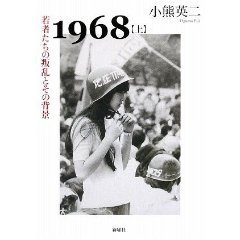
小熊英二の『1968』がボロクソに言われています。ホンマにそんなにひどい「誤読」「誤用」「捏造」「歴史偽造」満載本なのでしょうか。私自身はまだ読んでいません。本が出てすぐに図書館に予約を入れましたが、いまだに音沙汰なしです。それだけ人気があるということなのでしょう。いや、価格が高すぎて個人での購入をためらう人が多い、ということなのかも知れません。
「ボロクソに言われている」と書いたのは、私がたまたま目にした3つの「書評」(分量的には遙かに「書評」の域を超えているが)がそうだった、というだけの話しで、世間的には高い評価を得ているのかも知れません。3つの書評とは『ピープルズ・プラン』48号の「東大解体はきらいですか」(安藤紀典)、『運動<経験>』30号の「<1968>論議」(天野恵一)、『金曜日』09.12.25号の「『1968』を嗤う―」(田中美津)。
安藤は自身が直接関わった東大闘争の評価をめぐって、天野も自身が参加した中大闘争の経緯をめぐって、小熊の事実誤認を激しく指弾しています。田中は、田中自身が一章設けて取りあげられていることもあって(そうらしい)反応も激しい。小熊の田中とリブに対する「無知」「無法」ぶりをコテンパンにやっつけています。
それぞれ「身に降る火の粉ははらわにゃならぬ」とばかりの「返し業」。するどく決まっているように見えます。小熊先生危うし。でも3つの「書評」を読んで率直に感じることは、史料しか目を通さない小熊より、その現場に居た当人が当時のことをよく知っているのは当然のことじゃないの、ということです。これでは「フェアな争い」とは思えません。(べつに「争って」いるわけじゃないけど)。
その意味で、1968年の経験者には、自分の経験したことは勿論のこと、自分が経験していない「他者の経験」もふくめて「1968」とはいったい何だったのか、ということについて語って欲しいと思う。その結論が小熊の結論と違うならば、なぜ違うのか、小熊の見方のどこが間違っているのか、という議論を発展させて欲しいのです。
小熊の「1968」運動の総括(?)は、「自分探し」の運動であり、結果として「消費社会」を準備した、というような内容だといいます(読んでないからよくわかりませんが…)。だとすれば、いかにも当世流行のニューレフト批判(=「新自由主義との親和性」などの批判)に乗かった「いかがわし」総括です。でも、小熊にはそう言わせておけばよいでしょう。問題は「1968」を体験した者、それを継承する立場に経つ者が「1968」をどう総括するのか、時代の中に位置付けるのか、ということではないでしょうか。『1968』の個々の運動の記述・評価をめぐる「争い」よりも、そっちの方が大事なことではないかと思わざるをえません。
全共闘運動から40年を経て、なおもその評価が定まっていないというのは、決して現代史研究者の怠惰のせいではないでしょう。全共闘運動や「1968」がいまだ続いていることの明かしです。三つの書評の筆者たちが本当に言いたかったことは、そのことかもしれません。
なお、紹介した3つの「書評」の中で一番読み応えのあったのは、田中美津さんのものでした。小熊の無知をバッサリと斬る大事な二ヶ所の場面で、本ブログでも紹介した西村光子さんの『女(リブ)たちの共同体』が紹介されています。田中さんが西村さんの本を高く評価していることがわかる文章です。
さて、私のケータイに京都市図書館から予約本が揃ったという案内がくるのはいつのことだろうか。
投稿時間 : 10:55 個別ページ表示 | トラックバック (0)
この書評は、季刊『ピープルズ・プラン』誌の43号に掲載するために書いたものです。

読んでいて胸にズキンとくる部分があった。痴呆の母親を自分の手であやめ、自らも自殺をはかって一命を取り留めた京都府の男性(当時 五四)の事件を紹介した部分である。男性は母の介護のために仕事を辞め、失業給付も底を突き、生活保護申請も断られ、住んでいたアパートの家賃も払えなくなり、最後の選択として「愛する母をあやめ」自らも死のうとした。底冷えが一段と厳しい京都の冬の夜のことである。
介護の困難を要因にした殺人事件は近年増えているが、私が、本書のこの部分を重苦しい思いで読んだのは、実はこの事件は、私が住む町内で起こったことだからだ。男性と母親が暮らしていたアパートの前の道はよく通っていた。事件の現場となった河川敷のサイクルロードもよく利用していた。しかし同じ町内に住みながら、私にはこの親子の貧困は「見えて」いなかった。私に出来たことは、ただ事件の後、現場で手を合わせることだけだった。
本書の中で著者は、日本は貧困問題(解決)のスタートラインにすら立っていない、と繰り返している。著者のこの厳しい認識は、私の町内で起こった悲劇を、自治会(町内会)も福祉協議会も事前にフォローできていなかったことを考えると、現実と合致していると言わざるをえない。
本書は、三層(雇用・社会保障・公的扶助)に張られたセフティネットの破れ目からまるで「すべり台」を滑り降りるように「落下していく人びと」と日々接している著者が、「その人たちの視点から物事を捉え直し」「そこからしか見えてこないもの」を貧困が「見えない」人々に提供しようという試みである。
新書版でありながら事例、データ、書籍紹介など豊富で、さらに著者の温かな人間学にも随所で接することができる。これから共に貧困問題解決のスタートラインに立とうとする者にとっては絶好のインデックスとなっている。
自前の論理で「貧困」を可視化
前著の『貧困襲来』もそうだったが、著者のオリジナリティは、既成の言葉にたよって現実を批判する立場に甘んじることなく、現実との格闘の中から現実を暴くために必要な言葉と論理を自前で作りだしているところにある。その立場は本書でも貫かれている。
例えば「五重の排除」。この聞き慣れない言葉は、貧困を自己責任で語る立場に対するアンチから作られた言葉で、貧困の背景には、(1)教育過程からの排除(2)企業福祉からの排除(3)家族福祉からの排除(4)公的福祉から排除、そして(5)自分自身からの排除がある、とする論理である。
これまでも(1)~(4)は教育の機会不平等やセフティーネットの機能不全として指摘されてきた。しかし(5)の「自分自身からの排除」とは何か。これは著者のオリジナルの言葉である。それは、貧困は「あなたのせい」という世間の自己責任の論理を内面化して「自分のせい」と思い込んでしまう状態をさす。その場合「人は自分の尊厳を守れずに、自分を大切に思えない状態にまで追い込まれ」、さらに「自分の不甲斐なさと社会への憤怒がみずからの内に沈殿し、やがては暴発する」。貧困者と日々接している者ならではの眼力である。残念ながらこの鋭い観察は当たってしまった。
貧困の現実を可視化する自前の言葉と論理はそれだけではない。〝溜め〟もまた貧困者とその境遇を理解するためのキーワードである。いや、著者にとっては〝溜め〟の有る無しは「貧困」と「貧乏」を区別するキーワード中のキーワードですらある。
では〝溜め〟とは何か。本書によれば〝溜め〟とは「溜池」の「溜め」のことである。大きな溜池があれば日照りでも慌てることはなく作物を育てられるが、小さいな溜池だと作物を枯らしてしまう。ようするに〝溜め〟は外からの衝撃を緩衝し、さらにそこからエネルギーを汲み出すことができるものである。
人間という作物にとっても成長するためには〝溜め〟は必要だ。先ずはお金という〝溜め〟だ。しかし、それだけではない。人間関係の〝溜め〟も大切である。家族、親族、友人など。さらに精神的な〝溜め〟も必要だろう。「やればできるさ」という精神的な自信、ゆとりがそれである。貧困とはこれらが総体として剥奪されている状態で、単にお金が無い状態を示す「貧乏」と「貧困」の違いはここにある、というのが著者の立場だ。
あいまいな「強い社会」
まだ貧困問題も格差問題もポピュラーな問題ではなかった時代から、それが社会的に必要であるとの信念から、野宿者の自立支援活動を積み重ねてきた著者は、「すべり台社会」から脱出した将来社会像について、決して大風呂敷を広げない。「大きな話しを引き寄せるのは、個々の小さな活動である」との信念からだ。そこには著者の誠実さが見える。そして、自ら「たすけあいネット」を作り出しつつ、同時に「公(おおやけ)」に異議申し立てをする。その二つが交わる地点を包括して「つよい社会」と位置付ける。しかし、この言葉は、今一こなれていない印象をもつ。
「つよい社会」とは、人々に〝溜め〟が保障された社会である。それにより前向きな努力の意欲が生まれ、潜在能力が発揮できるようになる。要するにそれは、新自由主義や「第三の道」が理想に掲げながら、実現することに失敗した「活力ある競争社会」を市民の主導で実現しようということなのか。それとも、〝溜め〟の有る無しに関わらず、あるいは〝溜め〟や前向きな努力に背をむける者であっても、無条件に生存が保障される社会のことなのか。
こうした議論は著者の好むところではないかも知れない。「今はスタートラインに立つことが先決で、目的地を論ずる時ではない」と叱られそうである。しかし、目的地が明らかになることによって、逆にスタートラインが鮮明になることがあるかも知れない。ひょっとしたらもう勝手にスタートを切っている走者がいることも。
湯浅誠著 『反貧困―「すべり台社会」からの脱出』
発行:岩波書店
2008年4月
定価 740円+税
投稿時間 : 23:20 個別ページ表示 | トラックバック (3)

2007年4月24に行われる「全国いっせい学力テスト」に不参加を決定した愛知県犬山市の教育委員会が緊急出版した『全国学力テスト、参加しません。』(明石書房、1200円)を読みました。とてもいい本でした。
そこには、「教育」という営みは「競争」とは相容れないものだ、という確固とした信念が書かれていました。私たちは、子供を「競争」させれば学力が向上すると思いがちですが、それはまったく根拠のない話しなのです。「競争」はむしろ初期段階の子供たちを勉強嫌にし、子供が学ぶ楽しさを体得することに対して、マイナス作用しかもたらさない、とのこと。確かにその通りですよね。
また、戦後日本の公教育(学校運営)の主体は、地方自治体であり、文科省と方向が違った場合、自分たちが正しいと思う方向に進む権利がある、と語られていました。今回の学力テスト「不参加」の決定は、犬山市が「特別なこと」をしているのではなく、文科省や犬山市の小中校を除く、全国の99.96%(学力テストに参加する学校の率)の学校の方が、戦後教育の原則から外れた「特別なこと」をしているのだ、ということがよく分かりました。

犬山市の教育委員会について色々と感動したあと、わが街・京都市の教育について考えてみようと、『奇跡と呼ばれた学校―国公立大合格者30倍のひみつ』(荒瀬克己、朝日新書)を読んでみました。電車の中で30代中頃の女性が、小さな子供をほったらかしにして一心不乱に読んでいたのを目の当たりにして、これは目を通しておかなくちゃ、と思った本です。
著者である堀川高校校長の荒瀬さんという人は、悪い人ではない、という印象を持ちました。与えられた職務をまっとうするために、努力をする人のようです。また、堀川高校のモットーである「すべては君の『知りたい』からはじまる」も、犬山市の「自ら学ぶ力をもった子を育てる」方針と、重なる部分があるように思います。ひところ盛んに言われた「新しい学力」概念ということなのでしょうか。
しかし、本書を読んで(読む前から)疑問に思うことは、「国公立大学への合格者を増やすことは、そんなに価値あることなのか?」ということです。荒瀬さんは、そうし批判を心得てか、合格者を増大させることが目的ではなく、あくまでも生徒の進路希望をかなえることが学校の役割だ、なんて、カッコイイことを言っています。
しかし、こうした本が出版されるのことも含め、堀川高校が注目されるのは、国公立大学への合格者の増大があったればのことです。ここがやっぱりポイントなのです。だから京都市教委は、自分たちがすすめてきた「教育改革」の成功例として堀川高校を前面に押し立てるのです。
しかし、国公立はおろか、およそ大学進学というものに興味がなかった私のような者には、「国公立大学の合格者が30倍、―それが何か?」(大前春子)です。堀川高校の教育目的は「次世代のリーダーの育成」だそうですが、この目的達成の数値基準が、国公立大学への合格者数だとすると、堀川高校は、次世代のリーダーの条件は、国公立大で教育を受けたもの、と言っていることになります。
格差社会が問題になっている中で、堀川高校がいったいどのような役割を果たそうとしているのか、ホノ透けてみえる本でした。
投稿時間 : 16:34 個別ページ表示 | トラックバック (0)
■豊かな筆致で「リブ」を追体験

読む前にちょっとした先入観があった。「リブ」と「フェミニズム」に関する本?「フェミニズム」はもちろん「リブ」にも一知半解の自分には、きっと読むに骨が折れるに違いない。しかしその先入観は読み始めてすぐ吹っ飛んだ。面白いのだ。「リブ」や「フェミニズム」に特別の関心や知識がない者でも読めるのだ。いや「読ませる」ように書かれている、と言った方がいいだろう。それは著者がこの本を誰にむけて書いているのかに関わる。
「…ほんの30年前に、全身全霊をかけて共同性の構築に関わった女たちがいたんだよと、現代の女たちや若者たちに伝えたい…」。
伝えるための工夫がある。ドキュメントという方法を取り入れたのがそれだ。「リブ」たちが著した本、ビラ、宣言のたぐいが、ふんだんに提供される。足りない部分は著者が、当時の活動家に直接インダヴューする。そして、何より「たつのこ共同保育所」という著者が直接関わった共同体(コレクティブ)の体験が率直に語られる。
これらを手際よくならべて、「リブ」をリアルタイムで経験していない者にも、まるでその渦中にいたかのように錯覚させてくれる著者の筆力には感嘆させられた。
■「リブ」と「連合赤軍」
女たち(リブ)の「コレクティブ」を歴史的に考察した中で、個人的に一番興味をそそられたのは、「リブ」と「連合赤軍事件」の関連を考察したところだ。「連合赤軍事件」は、当時高校生だった私にも衝撃だった。私は、リンチ殺人が明るみに出て世間が騒然としてしているあの年の3月、春休みを利用して上京し、東京の千駄ヶ谷区民会館で開かれた「14名の兵士を追悼する集会」(主催「赤色救援会」=もっぷる社)に参加した。
今にして思えば、それは自分の「生き様」を定めた決定的瞬間だったと思う。
そして、当時すでに「リブ」のリーダーであった田中美津。彼女も「連合赤軍事件」に衝撃をうけ「連合赤軍は自分の中にもある」と宣言する。新左翼運動が東大安田砦の攻防で落日を迎えていた時、「軍事の高次化」(赤軍派)とは対極にある「日常性の革命化」(リブ)という行き方を選択した「ハズ」であるにも関わらず、である。この宣言を契機にして「リブ」の運動は事実上終わるのであるから重要だ。
田中の言う「連合赤軍は自分の中にもある」とはどういうことか。著者はこの言葉を手がかりに「リブ」の「コレクティブ」と、連合赤軍の山岳ベースという「コレクティブ」の、本来対極にあるはずの二つの「コレクティブ」が、どこで重なり、どこでズレているのかの考察に向かう。田中自身が永田洋子の誘いで山岳ベースを訪ねていたという事実の紹介も含め(これも私にとって衝撃だった)、この謎解きに有無を言わさずに読者を引きずり込んでしまう著者の筆力は圧巻だ。
結局、連合赤軍は内部崩壊し、「リブ」と全国各地に生まれた「コレクティブ」も一部を残して流れ解散に行き着く。連合赤軍の崩壊の原因は「共同体」の閉鎖性にあった。これには誰も異論はないだろう。ではリブの「コレクティブ」の結末はどこに原因があったのか。この時、著者は一般に流布されている「共同体」や「集団生活」その原理自身に原因を求める立場(本書では加納実記代や上野千鶴子がそうだとされる)を拒否する。
そして一つの結論を導き出す。共同体の中に個人の居場所がなかったこと。著者の表現をそのまま引けば「前近代」への逆戻りである。しかしリブが「先進的だった」のは、そのことに気付いた時、さっさと再びリブの出発点である「個」(あたし)に戻ったことだ、と付け加えることを著者は忘れない。
■団塊の世代による新たな「コレクティブ」の挑戦
本書を読んで、いくつもの場面で、自分の体験が呼び覚まされた。平場(平等)であるべき「コレクティヴ」(広義の意味)の内部にも、権力関係が発生するというのは、多くの者が体験ずみだろう。「コレクティヴ」5年周期説も、実感である。無理は禁物なのである。大げさに言えばこの結論は、社会主義の壮大な失敗から得た教訓でもある。
しかし、本書を読んで気付いたのは、私はもう15年以上も「無理は禁物」という教訓にのみ忠実に過ごしてきたのに対して、著者は「個」(あたし)から出発して再び「共同体」に向かう新たな物語を模索しているということだ。わたしより年長の著者のこのエネルギーには驚嘆する。
リブは、団塊の世代が恋愛、結婚、子育てにさしかかる時、「男との関係」「産むこと」などををめぐる広大な女の憤激を背景に「コレクティブ」を発生させた。その世代がいま「定年」を迎え、広義の意味での「終の棲家」を求めはじめている。著者が終章で紹介している「住まいの形」をとる「コレクティブ」がそれだ。著者が紹介するような環境、ケア(福祉)、プライバシー保護を備えたそれは「完璧」であろう。「共同で生活することが好きな人」だけがあつまれば「無理」も生じぜす「仲間殺し」も発生しない。
しかし正直に言って違和感はぬぐえない。一つは、それはミドル階級の排他的な新たな閉鎖社会にすぎないのではないかという疑念。同じことだが、著者が最期に強調している「諧謔精神」とバランスが取れるのかという疑問。
「社会の閉塞状況をぶち破るものは、社会を支えるつっかいをはずし、それに寄りかかっていた自己をも笑い飛ばす諧謔精神である」。
それに寄りかかっていた自己を相対化するとは、そこから社会的に排除されてきた人々(若者、女、障害者などなど)と出会い、それを鏡にしてはじめて可能なのではないか。複数の鏡がある「コレクティブ」こそ、「リブ」を引き継ぎ、「リブ」を超える「コレクティブ」(共同体)なのだと思う。
■『女(リブ)たちの共同体(コレクティブ)―70年代ウーマンリブを再読する』
■西村光子著/社会評論社/1700円
投稿時間 : 11:39 個別ページ表示 | トラックバック (0)

「嫌韓」「嫌中」の若者の背後にあるもの
小泉首相が靖国神社を参拝した八月十五日、二十五万人もの人々が靖国に足を運んだが、そこには多くの若者の姿があったという。彼らの一部がそれを「靖国参拝オフ」と呼ぶことから分かるように、彼らの多くはオンライン(インターネット)を住処としている。
インターネットの世界では、中国や韓国を批判する「嫌韓」「嫌中」のサイト、ブログ、掲示板の類が急増している。それをソースにした『マンガ嫌韓流』は一巻、二巻あわせてが六七万部が売れた(出版社の公称部数)。他方、日本のネットの動きに呼応するかのように韓国、中国でも若者の「反日」ナショナリズムが電網世界を走り抜けている。こうした東アジア・日韓中三国における若者を担い手とした「ナショナリズム」の噴出、相剋をどのようにみるべきか。
続きを読む "『不安型ナショナリズムの時代―日韓中のネット世代が憎みあう本当の理由』"
投稿時間 : 15:06 個別ページ表示 | トラックバック (1)
ボンボン政治家の「闘う政治家」宣言

安倍晋三氏と私は同い年である。私は1954年の4月生まれで、安倍氏は9月。今年(06年)共に52歳である。私たちの世代は、安倍氏も述べているように「団塊と新人類にはさまれた、どちらかというと影のうすい世代」である。その「影のうすい世代」の中から、わが安倍晋三クンが、いよいよ総理大臣に挑戦するという。同じ世代として感無量だ。
安倍晋三氏は、元首相の孫、元大臣の息子ということから「苦労知らずのボンボン」と言うイメージが強い。「北朝鮮拉致事件」「靖国参拝」などでの硬派な言動にもかかわらず、人柄としては「いいとこの坊ちゃん」のイメージが抜けない。本人もその点を気にしてか、本書で、自分を「闘う政治家」と宣言して「ボンボン」メージの払拭に懸命である。
しかし、残念ながら、本書をいくら読んでも、闘うことによって実現しよとする社会像がイマイチ見えてこない。「日本の真の独立」とか「損得を超えた価値」とか「家族の絆」とか「郷土愛」とか「愛国心」などなど、保守派の定番キーワードは頻繁に出てくるが、言葉が上滑りしている感は否めない。
むしろ、「社会保障」に関して述べた部分の方が、意外にも「…やみくもに小さな政府をもとめるのは、結果的に国をあやうくする」との考えが打ち出されており、真っ当である。安倍氏はイギリスのチャーチルを尊敬していると言う。「社会保障」重視の政治家だ。「再チャレンジ可能な社会」などの政策的立場が、単に総裁選用のリップサービスではなく、この尊敬する師の教えに沿ったもであるならば、おおいに歓迎できる。安倍氏は、安全保障問題より社会保障問題のほうが、本当は得意なのではないか。
最後に本書のタイトルについて。ネットで「美しい国」と検索したら『美しい国日本の使命』という本がヒットした。世界基督教統一神霊協会の日本初代会長・久保木修己氏の遺稿集だという。同協会系の合同結婚式への安倍氏の祝電といい、似たタイトルといい、両者の関係はどうなっているのか。「説明責任なんか知らない!」と思っているとしたら、アベちゃんは、やっぱり「ボンボン」だ。
投稿時間 : 15:27 個別ページ表示 | トラックバック (0)

●ノン・エリートへの一貫した「優しい眼差し」
熊沢さんの書物は、どれも、働く者への優しい眼差しに貫かれている。本書中でも、不安定な雇用形態で一生働かねばならないかも知れないフリーターたちにむけ、こんな温かい言葉をかけている。
「…将来の展望を喪って落ち込んだり、とりあえず刹那的な遊びやお笑いに日を過ごしたりするのも、ある意味では当然でしょう。何年も『ハンズ』としてのフリーター生活を続ける若者のまじめさに、私は、むしろある意味では敬意を覚えます」(P84)。
フリーターの存在を「困ったこと」、あるいは正社員にむけてそこから「脱出させるべきもの」と描く学者が多い中で、「敬意を覚える」と書く学者を、私は、熊沢さん以外に知らない。
この温かい眼差しは、熊沢さんの「フリーター支援策」の中にも表れる。
「あえて言えばフーターがフリーターのままでも生活していけるような支援政策が必要不可欠です」(P97)
フリーターを正社員にすれば問題が解決するかのような議論が多い中、熊沢さんの立場は違う。正社員として「燃えつきて」しまった若者が、フリーターとなる例が多いからだ。雇用形態にかかわらず、若者がちゃんとした生活ができるような労働環境にしていくこと、これが本書で熊沢さんが主張していることだ。
全編、温厚な語り口で書かれているが、熊沢さんがキッパリとした口調で相手を批判した箇所がある。山田昌弘さんが『希望格差社会』の中で「正規雇用」と「非正規雇用」への分岐はグローバル経済下では「必然・宿命」、と論じたことへの批判である。
山田さんがグローバル時代の「中核的労働」と「単純労働」への分岐に雇用の二極化の原因を見るのに対し、熊沢さんは「労働の質」の分岐を労働者間の差別的な処遇へと結びつけない力を労働組合は歴史的に持って来たし、又、持つべきだと言う。
労働組合の力が限りなく衰弱している日本では、熊沢さんの言うことは「引かれ者の小唄」に聞こえるかもしれない。しかし、「不安定な雇用はゴメンだ!」と立ちあがり、CPE(初期雇用契約)を撤回させたフランスの若者、労働組合の闘争を見ると、グローバル下の雇用の二極化、不安定化は「必然」でも「宿命」でもなく、それは、若者、労働者、市民で決められることなんだ、ということに気づかされる。本書の射程の長さは、ここでも、証明されている。
■ 『若者が働くとき』(熊沢誠)
■ ミネルヴァ書房 2000円
投稿時間 : 23:25 個別ページ表示 | トラックバック (2)
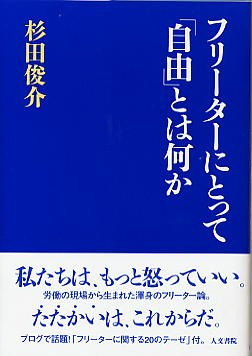
この本の特徴を一言で言えば、フリーター自身の筆による「フリーター階層の権利宣言」ということになろうか。著者は、1975年生まれというから団塊Jrそのものだ。大学院を修了しているので、一般的にイメージされる「フリーター」とはちょっと立場が異なるかも知れない。だが、魂はまぎれもなく「フリーター」だ。
本書の主張が、他の類書とくらべて傑出しているのは、フリーターの存在を「困ったもの」、そこから「脱出させてやるべきもの」という考えを退けて、「フリーターがフリーターのままでも生きていける社会をめざす」と宣言していることだ。この点が(名前をあげて恐縮だが)他の売れ筋の本(『希望格差社会』や『下流社会』)とはひと味もふた味も違うところだ。
そう言い切る著者には、ある信念がある。それは「存在の価値」は「経済的な価値」や「自立の価値」に優先する、という考えだ。ちょっと難しそうだが、こういうことだ。
「たかがお金がない、安定した仕事がない、経済能力がない、それらの不足と欠損が、あなたが『生きる価値がない』ことを意味することは絶対にない、絶対に。」(p14)
「フリーター」だけではない。「生きる価値がない」という眼差しを、日々むけられている全ての者たちへのエールの本なのだ。
「格差社会」が流行語(ブーム)になり、それに便乗して数多の本がでている。相変わらず「若者の労働意欲のなさ」をバッシングするものが多いが、最近は、企業側の採用政策に問題があると、正しく指摘をするものも増えてきた。(例えば『「ニート」って言うな』)。だが、そうした論者の多くも、今後については、学校での「職業教育」の重視や、個人の「能力開発」を公がサポートする体制の整備を提言するにとどまっている。
「たとえ能力が無くとも、そこそこ生きていける社会」という著者の「宣言」を、いささか眩しく感じるとすれば、それは、闇がまだ深いことの逆の証明なのかも知れない。
■『フリーターにとって「自由」とは何か』(杉田俊介)
■人文書院
■価格 1600円
投稿時間 : 17:52 個別ページ表示 | トラックバック (1)
玄田有史、曲沼恵美 著
発行:幻冬社
定価:1500円
ニートを「社会問題」にした古典
いまや「古典」とも言うべき書物かもしれない。この本が世に出たのは昨年の夏。以降、怒濤のような「ニート」ブームが続いている。実際、テレビのワイドショーを媒介にしてか、「ニート」という言葉は今や誰もが知るものとなった。しかし、その使われ方は、決して著者たちの意図を汲んだものとは言えそうもない。「ニート=仕事も勉強もしないで、親や社会に寄生している者」という、若者バッシングの新たな言葉として使われているのが実状だろう。
そこで、である。「ニート」に対する正しい認識を得るために、この本にあたることは意義あることかも知れない。そこにはきっと、大衆によって「歪めて」流布、受容される前の「正しい定義」や「解釈」があるはずだ。こう期待して本書をひもとく人は、肩すかしを食らうかも知れない。
確かに、ニートが「NEET」であり、それは「Not in Education(学校教育) Employment(雇用) or Training(訓練)」の頭文字を取ったものだとか、それがイギリスの労働政策の用語だったとか、そういうことはわかる。
しかし、肝心の日本の社会におけるニートの存在、その定義、生み出される背景などについて、著者たちは、複数の視点を交差させながら論じ、また、当事者に直接インタヴューを試みて実像を紹介しながら、断定めいたことは慎重に避けているのだ。
それは、著者の一人である玄田有史が、前作『労働の中の曖昧な不安』(二〇〇一年、中央公論新社)で、若年失業者の増加を「若者の働く意欲の低下が原因ではなく、中高年雇用者の既得権が若者の就業の機会を奪っている」と鋭く分析した「切れ味」と比べると、かなり「あいまい」に見える。また、同じく玄田が新著『十四歳からの仕事道』(二〇〇五・一、理論社)で、「ニート予防」として中学二年生にむけて熱く語った実践的指南の方向は、本書ではまだ「対策」の中の一つという域を出ていない印象を持つ。
しかし、こうした本書の「あいまいさ」は、新しい事象に対して、時間をかけて、異なる考えの人々と共に迫っていく、という著者たちの姿勢の表れと受け止めたい。だからこそ、本書は多方面で受け入れられ、時には歪めて受容されながらも、結果として「ニート」を社会問題として押し上げる起点となったのだ。
「若者自立・挑戦プラン」の傲慢さ
いま、「ニート」ブームにまぎれて、あるいは「フリーター対策」と称して、政府も様々な若者の「自立」や「挑戦」を支援するプランを出してきている。「学校でのキャリア教育の強化」「日本版デュアルシステム」「若者二〇万人常用雇用プラン」など、「若者自立・挑戦プラン」(および、その実効性・効率性を高めるための「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン」)がそれだ。
その目的は「働く意欲が不十分な若年者やニートと呼ばれる無業者などに対して、働く意欲や能力を高め」、「産業競争力の基盤である産業人材の育成・強化を図る」というものだ。
これは、新自由主義によってはじき出された「ニート」や「フリーター」を、再びフルイにかけて、その一部を新自由主義の推進役として再び取り込もうという政策に見える。しかし、ここではその点については触れない。
むしろ問題にしたいのは、この「若者自立・挑戦プラン」が前提にしている若者観だ。つまり「ニート」や「フリーター」を「労働意欲の低下した者」という旧態依然とした若者観で眺め、そこから、若者を叱咤激励して「働く意欲や能力を高めよう」という、その傲慢さだ。
玄田は、こうした若者観を本書の中でこう批判している。
「理解しにくい若者の問題を、意欲の低下として片づけることができれば、大人の多くは安心なのだろう。理解できたとして安心して職業意識を啓発する作業に没頭できる。しかし第三者が人の意識や意欲を変えようというのは、多くの場合、傲慢以外の何ものでもない。本人すらわからない心の奥底の意識や意欲について、他人が決めつける権利はどこにもない」
私はこのあたりが、いま「ニート」「フリーター」をめぐる攻防の最前線なのだと思う。
エリート的価値からの「自立」
政府の若者観は、裏を返せば、働く意欲や能力が高く、産業人として競争の中を勝ち抜く意欲のある者こそが「自立した人間である」ということになる。そのことは「若者自立・挑戦プラン」の中でもはっきりと書いてある。「目指すべき人材像」は、「真に自立し社会に貢献する人材」「確かな基礎能力、実践力を有し、大いに挑戦し創造する人材」だと。
九〇年代の後半以降、日本社会が急速に息苦しくなったのは、こうした価値観が社会全体を一元的に覆ってしまったからではないか。庶民の独自の文化・価値観が後退し、エリート的価値観の承諾が全人口に迫られつづけた。その結果、価値に沿わぬ者は「おちこぼれ」「負け組み」のレッテルを頂いた。そして今度は「ニート」だ。
「ニート」の自立(と支援)は必要だ。でもそれは、どのような自立なのか。エリートの価値観に沿ったそれか。それとも、エリート的値観からの自立、ノン・エリート独自の文化を創造する方向への自立(と支援)か。
玄田は、前述した新著の中で、「人生の充実」ということについて、こんな内容を中学二年生に語っている。
「もっとはっきり言えば、個性や専門性などなくとも、十分、充実した人生をおくることはできる。ここでいう『充実』とは、特別にすぐれた才能をもった人間でなくとも、自分なりに出来ることを精いっぱいやって生きることで得られる達成感のことです。個性や専門性なんかなくとも、ちゃんと生きていけるのです」。
「特別にすぐれた才能をもった人間でなくとも」なんとかやっていける世界。それがノン・エリートの世界であろう。玄田が構想する「ニート自立」もそれと重なると、私は思う。
玄田は、新著の最終章をわざわざ「特別章」として「学校をやめた人々」(中卒者と高校中退者)へのメッセージに当てている。「ニート」や「フリーター」が、中卒者と高校中退者に、そして経済的に苦しい家庭の出身者に多いことは、すでにデーター的にも明かになっている。
季刊『ピープルズ・ピラン』 NO31(05/08/25)掲載
投稿時間 : 22:39 個別ページ表示 | トラックバック (0)
『現代の理論』復刊

ウワサに聞いていた『現代の理論』の復刊にむけた準備号が送られてきた。大先輩の小寺山康雄さんからである。準備号は50ページ足らずの小冊子。巻頭の座談会は、Web siteで公開している。ほかに37人ほどの人が一文を寄せている。これもけっこう読み応えがある。
「現代の理論」には個人的には義理も恩もなにもないが、その志には敬意を表したい。協力して頂ける方は、以下を参照して申し込まれたい。
■季刊『現代の理論』
<創刊準備号>
・編集員座談会 [現代の理論]のめざすもの
・沖浦和光・橘川俊忠・住沢博紀・小寺山康雄・池田祥子・宮崎徹
<04秋 創刊号> 九月二〇日発売予定
・総特集 日本 どこからどこへ?
・創刊記念対談 人間の歴史を文明史的に捉え返す(尾本恵市×沖浦和光)
投稿時間 : 23:12 個別ページ表示 | トラックバック (0)